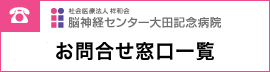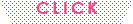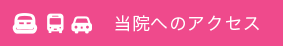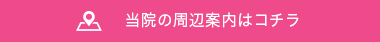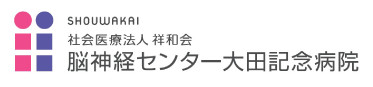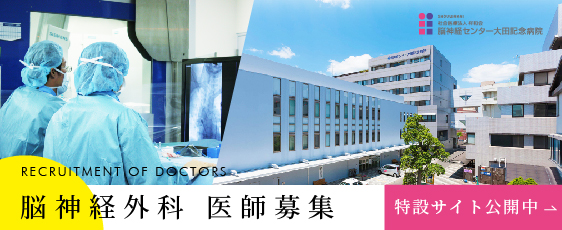大田記念病院の診療科
大田記念病院の診療科
-
脳神経外科


-
脳神経センター大田記念病院 脳神経外科は開院以来、最先端の脳神経外科を追求しています。その治療成績は国内有数のレベルにあります。
診療に携わる各医師はそれぞれに特化した専門性を有しており、脳神経疾患全般に対応可能です。診療内容
 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・脳腫瘍・水頭症・低髄液圧症候群・抹消動脈狭窄/閉塞・脳動脈奇形・頭部外傷(急性硬膜下血腫・慢性硬膜下血腫)・三叉神経痛・顔面痙攣・不随意運動など。
脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・脳腫瘍・水頭症・低髄液圧症候群・抹消動脈狭窄/閉塞・脳動脈奇形・頭部外傷(急性硬膜下血腫・慢性硬膜下血腫)・三叉神経痛・顔面痙攣・不随意運動など。
●未破裂脳動脈瘤、無症候性内頚動脈狭窄・頭蓋内主幹動脈狭窄等に対する予防的治療については、患者さんの意思を最大限に考慮して治療を行います。
●良性腫瘍の場合、手術・ガンマナイフ・経過観察のどれがいいか、3つの選択枝から患者さんの視点で共に考え、治療方針を提示できる体制を整えています。科目の特徴

当院では、脳血管障害に対する24時間対応の救急体制をとっております。脳梗塞に対するt-PA治療や脳血管内治療による血栓回収術、脳出血に対する開頭術、および内視鏡手術、くも膜下出血に対する脳血管内治療によるコイル塞栓術や開頭術などが行える体制となっています。
また、脳血管障害に対する治療法については、開頭手術もしくは脳血管内治療を選択することができます。たとえば、頸動脈の狭窄に対する、内膜剥離術もしくはステントを使った血管拡張術、脳動脈瘤に対しては、開頭クリッピング術もしくはコイル塞栓術など、患者さんの状態に合わせて適切な治療選択ができます。医師
 ■脳神経外科部長 宮嵜 健史
■脳神経外科部長 宮嵜 健史
・日本脳神経外科学会専門医
・日本脳卒中学会専門医
・日本脳卒中の外科学会技術指導医
・日本脳神経血管内治療学会専門医
■脳神経外科専任部長・地域連携業務統括医師 佐藤 倫由
・日本脳神経外科学会専門医
・麻酔科標榜医
■中﨑 清之
・日本脳神経外科学会専門医
■郡 隆輔
・日本脳神経外科学会専門医
・日本脳卒中学会専門医
■片桐 匡弥
・日本脳神経外科学会専門医
・日本救急医学会専門医
・日本てんかん学会専門医・指導医
・日本臨床神経生理学会専門医・指導医(脳波分野)
・VNS実施資格認定
・The American Board of Clinical Neurophysiology(米国脳波認定医)
・日本定位・機能神経外科学会 機能的定位手術技術認定
■松田 和郎 [非常勤]表示を閉じる -
脳神経内科


-
Brain Attack 24-
24時間いつでも脳卒中治療に対応可能な診療体制をとっています。
●年間約1,300件(2020年実績)の脳卒中患者さんに対し脳神経外科と連携して治療に取り組んでいます。
●パーキンソン病など神経難病の鑑別診断と治療を行っています。診療内容
1)病歴(急に起こったか/緩やかに起こったか)
2)経過(急速に進行しているか/緩やかに進行しているか)などの問診
3)現在の症状(神経学的診察所見)
4)検査結果(血液検査、画像検査、筋電図検査)
を踏まえて、診断および治療を行います。
脳神経内科疾患は多岐にわたっております。
個々の患者さんに最善の医療を提供することを重視し、症例によっては大学病院等と連携し、診断・治療を行います。科目の特徴
脳神経内科では脳・脊髄・末梢神経・筋肉の病気についての診察を行います。
脳神経内科で診療にあたる神経疾患は
・脳血管障害(脳梗塞、脳出血)
・神経変性疾患 (パーキンソン病/脊髄小脳変性症/筋萎縮性側索硬化症/重症筋無力症)
・急性末梢神経障害(ギランバレー症候群)
・多発性硬化症、多発性筋炎、および全身性慢性疾患(内科疾患)に合併する疾患、
など多岐にわたります。医師

■脳神経内科部長 脳卒中センター長 寺澤 由佳
・日本神経学会神経内科専門医
・日本脳卒中学会専門医
・日本内科学会総合内科専門医
・日本臨床神経生理学会専門医(筋電図・神経伝導分野)
■脳神経内科副部長・脳血管内治療センター長 姫野 隆洋
・日本神経学会神経内科専門医
・日本脳神経血管内治療学会専門医
・麻酔科標榜医
■脳神経内科副部長・神経難病センター長 佐藤 恒太
・日本神経学会神経内科専門医
・日本脳卒中学会専門医
・日本内科学会総合内科専門医
・日本認知症学会専門医
・認知症サポート医
■久保 智司
・日本内科学会認定内科医
■佐藤 達哉
・日本神経学会神経内科専門医
・日本内科学会総合内科専門医
・日本臨床神経生理学会専門医(脳波分野、筋電図・神経伝導分野)
■井上 智之
・脳血栓回収療法実施医
・日本内科学会認定内科医
■福山脳神経医学研究所所長 郡山 達男
・日本神経学会神経内科専門医
・日本脳卒中学会専門医
■片岡 敏
・日本神経学会神経内科専門医
・日本脳卒中学会専門医
■齊藤 明子
・日本神経学会神経内科専門医
■岡本 美由紀
・日本神経学会神経内科専門医
■藤田 和久
・日本神経学会神経内科専門医
・日本認知症学会専門医
■庵谷 紘美
・日本救急医学会救急科専門医
・日本集中治療医学会集中治療専門医
■越智 俊樹
■下江 豊 [非常勤]
・沖野上クリニック院長
■髙橋 幸治 [非常勤]
■黒川 勝己 [非常勤]
・川崎医科大学 神経内科学教授
■石浦 浩之 [非常勤]
・岡山大学脳神経内科学教授
■中道 淳仁 [非常勤]t-PA治療の取り組み ~「脳神経センター」としての特徴・特色
脳梗塞を代表とする「脳血管障害」が脳神経センター大田記念病院において、入院の最も多い理由です。
脳血管障害(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・TIAなど)は、前触れがなく急に発症する場合も多く、数時間から数日で急速に病状が悪化することがあります。
●脳梗塞の急性期医療
1)t-PA治療
t-PA(組織性プラスミノーゲン活性化因子)は血管に詰まった血栓を溶かし、血流を回復させる薬です。脳梗塞発症4.5時間以内に投与すれば、大きな効果が期待できるとされています。
*使用禁忌項目対象者を除く。
t-PA静注療法により大きな改善をもたらした結果を多く得ています。
2)脳血管内治療
脳梗塞発症4.5時間を超えた、または、t-PA適応外の場合、脳神経センター大田記念病院では即座に脳血管内治療の適応についての検討を始めます。脳神経外科の医師との連携を密にとり、患者さんの救命および後遺症を最小限にできるように心掛けております。
脳神経センター大田記念病院では、脳卒中に対し24時間、治療可能な設備と体制を整えています。急性期脳梗塞に対してt-PA静注療法と脳血管内治療が補完し合い良好な成績をあげています。表示を閉じる -
脊椎脊髄外科


-
当院では脊椎・脊髄手術において、手術用顕微鏡を用いて積極的に低侵襲手術を施行しています。低侵襲手術は、従来の方法と比較して以下に示すような多くのメリットがあります。
1.傷が小さい。
2.組織への侵襲が少ない。
3.術後の痛みが少ない。
4.入院期間が短縮できる。
5.社会復帰が早い。
6.腰背部筋肉の萎縮が少ない。
さらに、腰椎椎間板ヘルニアに対する「経皮的椎間板内酵素注入療法」や、頸椎椎間板ヘルニアに対する「頸椎人工椎間板置換術」などの最新の治療を受けることができます。診療内容
脊椎ならびに脊髄・脊髄神経の病気や外傷で、痛みやしびれ、筋力低下、歩行困難などの症状がある方々の治療を行っています。
脊椎・脊髄の幅広い疾患について、脳神経センター大田記念病院にある最新の診断機器を使用し、専門的知識を有する医師が的確な診断を行います。
治療の主体は手術などの外科的治療ですが、痛みや痺れに対する内服治療、診断を兼ねた神経ブロック、慢性腰痛に対する筋力強化などのリハビリテーション、減量など日常生活に関係するアドバイスなどにも、積極的に取り組んでいます。科目の特徴
診療に携わる医師の資格が、日本脳神経外科学会指導医・日本脊髄外科学会指導医・日本整形外科学会専門医・日本脊椎脊髄病学会指導医・日本神経学会専門医と多岐にわたり、幅広い視野で診断・治療を行います。
手術用X線透視装置による術中3D画像と、実体模型を用いた術前計画、術中ナビゲーションシステム等で適正なインストゥルメントの設置を行っています。
脊髄動静脈奇形では顕微鏡手術のほか、当院の血管内治療グループによる超選択的な血管造影や塞栓術が可能です。当院は「脊椎脊髄外科専門研修施設」です。
脳神経センター大田記念病院は、2014年7月1日、一般社団法人日本脊髄外科学会の「脊髄外科訓練施設」に認定されました。それ以降、「日本脊髄外科学会認定医」の資格取得を目指す医師が、当院で研修を受け、実際の手術を通じて訓練を行ってまいりました。訓練施設の認定は、中国地方では初めてのことでした。
2022年4月、日本専門医機構より機構認定サブスペシャリティ領域として「脊椎脊髄外科医」が認定され、2023年4月からのカリキュラム開始を受けて、施設の名称が「脊椎脊髄外科専門研修施設(日本専門医機構サブスペシャリティ領域専門研修制度整備基準)」に変更となっております。
今後さらに、患者さんの首や腰の治療・手術に取り組むことはもちろん、この分野に進む若手医師の養成に貢献してまいります。医師

■副院長・脊椎脊髄外科部長 大隣 辰哉
・日本脊髄外科学会指導医
・日本脳神経外科学会指導医
■大田 泰正
・日本神経学会神経内科専門医
・日本脳卒中学会専門医
■酒井 恭平
・日本脳神経外科学会専門医
■吉原 拓馬
■西原 伸治[非常勤]
関係する症状
● 頚部痛・肩こり・背部痛・腰痛
● 上肢や下肢のしびれ・痛み・力の入りにくさ
● バランスが取れない・歩きにくさ表示を閉じる -
循環器内科


-
診療内容
当院には脳卒中で年間約1,200例の患者さんが入院されます。脳神経疾患と循環器疾患は非常に密接な関係にあり、脳梗塞全体での冠動脈疾患の合併率は約23%※、アテローム性脳梗塞だと約30%併発しています。頚動脈狭窄症の症例では冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)を併発している人が約40%(8.2~60% と幅広く報告されている)ととても多く、脳神経外科にて頚動脈狭窄症の手術を検討されている患者さんに対して、冠動脈疾患の検査も含めて精密検査を行っております。
さらに脳神経疾患で当院入院中・通院中の患者さんを中心に、循環器疾患のサポートも緊密に連携をとり行っております。
※Yamazaki T:et at Cire J,71(7):995-1003,2007科目の特徴
循環器内科は主に心臓および血管の病気の診断と治療を行う診療科です。高血圧、狭心症、心筋梗塞、心不全、不整脈、末梢血管疾患を主に治療を行っております。
【生活指導】
禁煙や禁酒、食事内容、運動など、医師や看護師、管理栄養士、リハビリ療法士などがチームとなって、患者さんの状態に合わせた生活習慣の見直しを行います。
【薬物治療】
冠動脈を拡げる、血管のれん縮を予防する、心筋酸素需要を減少させる、動脈硬化の進行を防止または抑制する、血の塊をつくりにくくする等の薬剤を組み合わせることにより、動脈硬化の進行を防止し、心臓の負担を軽くして症状の改善を行います。医師
■循環器内科部長 宮本 欣倫
・日本循環器学会循環器専門医
・日本心血管インターベンション治療学会認定医
・心臓リハビリテーション指導士
■循環器内科兼回リハ専従医 安田 廣太郎
■高畠 周
・日本循環器学会循環器専門医
・日本心血管インターベンション治療学会認定医
・日本内科学会総合内科専門医
■大田 知子
・日本内科学会総合内科専門医検査
【心電図】
安静時の心電図で脈の異常や心臓肥大、心筋梗塞等の診断を行います。
【負荷心電図】
階段昇降により心臓に負担をかけて、不整脈、狭心症の診断を行います。
【ホルター心電図】
24時間の心電図を持続的に記録し、不整脈、狭心症の診断を行います。
【ABI/PWV】
ABI検査とPWV検査は、手と足の血圧の比較や脈波の伝わり方を調べることで、動脈硬化の程度を数値として表したものです。
この検査を行うことにより動脈硬化(血管の老化など)の度合や早期血管障害を検出することができます。
【心臓超音波検査】
超音波により心臓の動きや、心肥大の有無、弁膜症の有無などを検査します。
【経食道心エコー】
食道は心臓の後ろを通っています。食道から超音波を用いて心臓の観察を行うことによって、より詳しい心臓の検査が可能です。脳梗塞の原因を調べる時にも行います。
【X線検査】
胸部レントゲン写真から心拡大や肺のむくみを調べます。
【心血流シンチ検査】
心臓の筋肉を養っている冠状動脈や、心筋の中の細い血管などの血液の流れを調べるため、心筋シンチ検査が行なわれます。【冠動脈CT検査】
冠動脈の狭窄をみる検査です。静脈から造影剤を注射して10秒間息を止めて64列MDCTという装置で撮影します。外来で行える検査です。
この検査で異常なしと診断されれば、冠動脈の狭窄はほぼ否定されます。狭窄が疑われた場合は、正確な診断には次の心臓カテーテル検査が必要になります。
諸検査により虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞) の疑いがあれば精密検査を行います。
【冠動脈造影検査(CAG)】
冠動脈造影検査(CAG)とは、心臓の筋肉を養っている3本の血管が狭くなっていないかを確認する検査です。当院では検査を手首から行い、最短3日間の入院で検査可能です。
手首・肘・足の付け根のいずれかにある動脈(どくどく触れる脈)の周囲に局所麻酔をします。動脈を穿刺(せんし)し、カテーテルというやわらかく細い管を心臓まで進めて、造影剤を冠動脈や左心室内に注入します。同時にカテーテルを通じて圧を測定します。今後の治療方針を決定するために極めて重要な情報が得られます。検査終了後はカテーテルを抜去し4~7時間圧迫止血します(挿入したカテーテルの太さにより違います)。
心血管インターベンション治療
【経皮的冠動脈インターベンション(PCI)】
経皮的冠動脈インターベンション(PCI)は、身体に大きな傷をつけることなく狭くなった冠動脈を拡げるために行う治療法です。
手術は足の付け根の大腿動脈または腕の橈骨(とうこつ)動脈や上腕動脈から「カテーテル」を入れ、冠動脈の狭くなったところまで進めて治療を行います。
先端に風船のようなものがついた管(バルーンカテーテル)を冠動脈の狭くなった部分に挿入し、そこで風船を膨らませることにより血管を押し拡げる治療です。
ステントという小さな網目状の金属の筒を血管に置くことにより、狭くなった部分を筒が支えて血管の中が拡がった状態を保持します。【経皮的末梢動脈血管内治療(PPI)】
下肢などの末梢血管の動脈硬化や動脈閉塞に対して、心臓の血管同様に病変部を風船で拡張し、場合によりステント(金属性の網目状の筒)を留置します。
【ペースメーカー植込み術】
脈拍が極端に遅い、ときどき心臓が停まってしまうといった徐脈性不整脈の患者さんに行う治療です。
鎖骨の下を通る静脈にリードを挿入して、心臓の中に到達させる方法です。 ペースメーカー本体は胸部(鎖骨より下の皮下)に植込まれます。手術にかかる時間は1~2時間ぐらいで、局所麻酔が使用されます。循環器内科 実績
項 目 2020年度 2021年度 2022年度 入院患者数 総数(入院数) 2,199 2,053 1,700 平均在院日数 6.13 5.72 6.39 検査 経胸壁心エコー図検査 3,399 3,514 3,396 ホルター心電図検査 739 684 580 心肺運動負荷試験(CPX) 223 225 336 心臓核医学検査(総数) 79 85 70 運動負荷 2 0 2 薬剤負荷 77 85 68 冠動脈造影CT検査 78 99 340 冠動脈単純CT検査 188 201 133 心臓カテーテル検査(総数) 183 178 115 治療 経皮的冠動脈形成術 104 95 60 末梢血管形成術 5 4 6 ペースメーカー植込み件数(新規) 10 13 15 植込み型心電計(ILR) 9 14 13 心大血管リハビリテーション新規患者数 46 58 74 心大血管リハビリテーション実施件数(総数) 1,546 1,728 2,023 心大血管リハビリテーション実施単位数(外来のみ) 4,583 5,162 6,027 表示を閉じる -
放射線科


-
画像診断の専門医が時間をかけて隅々まで画像をチェックすることにより、細かな所見についても見落としの危険性が減少します。
また、毎日多量の画像検査を見ているので、珍しい病気の画像所見についても豊富な経験を蓄積しています。診療内容
● X線写真・CT・MRIなどの画像検査の読影(検査結果の判定)
● 脳ドックを含めた外来診察
● カテーテル検査や造影CT検査の施行
● CT・MRIの検査方法についての指示
当院における放射線科の主な業務・診療内容は上記のように大分されます。
最近のMRIやマルチスライスCTなどの高度診断機器による検査には膨大な量の診断情報が含まれており、限られた時間で主治医が一人で診断するには無理があります。
外来・入院および診療科を問わず、安全な医療提供を放射線科の画像診断がサポートしています。科目の特徴
●3名の放射線科専門医が業務に当たっています。
外来検査の読影については、待ち時間が長くならないように迅速な読影報告書の作成に努めています。
●CTやMRIなどの画像診断機器と放射線科読影室の画像ビューワーがネットワークで繋がれており、検査後ただちに見ることができます。
また、過去の検査画像についても電子化されており、すぐに画像ビューワー上に呼び出して新しく撮像された画像と比較することが可能です。読影に必要な症状や血液データなども電子カルテ上で参照できるので、フィルムやカルテを移動する時間が不要で、その分素早く読影結果を診察医のもとに届けることができます。
●脳ドックについては神経領域を専門とする放射線科医が主に担当していることが特徴です。
MRI診断が正確である点と病気が発見されたときに外科手術に偏らないでより客観的に治療方針を検討できる点が長所です。病気に関して当方が必要性があると判断した場合やご本人からの希望がある場合には脳神経外科・脳神経内科・脊椎脊髄外科の診察を受けておいただきますが、未破裂脳動脈瘤などで定期的にCTやMRIを撮っていく必要がある場合には当科で経過観察を続けることが多いです。
●当院では最新のCTやMRIなどの画像診断装置を多数備えています。
近隣の診療所や病院からの検査依頼をお受けしています(画像診断機器共同利用)。 この際も当科専門医が適切な検査内容を指示して、検査後はご紹介いただいた主治医の先生宛に読影報告書を送付しております。医師

■院長・放射線科部長 田中 朗雄
・日本医学放射線学会専門医
・日本核医学会PET認定医
■小林 宏光
・日本医学放射線学会専門医
・日本核医学会PET認定医
■沼 真吾
・日本医学放射線学会専門医
■林田 稔 [非常勤]表示を閉じる -
内 科


-
診療内容
患者さんの訴え、あるいは症状がどのような臓器の異常からきているのか、または、どのような診療科の疾患に属するのかをみる総合診療科的な役割を果たしています。
メタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)に属する肥満・糖尿病・高血圧・脂質異常症の予防、治療を中心に診療を行っています。科目の特徴
脳神経センターの内科として、特に脳卒中の原因である、高血圧・動脈硬化・糖尿病などメタボリック・シンドローム(代謝疾患)の治療・予防に力を入れています。
医師
■内科部長 藤川 康典
・日本内科学会総合内科専門医
・日本糖尿病学会専門医
・日本老年医学会認定 老年病専門医
■小原 健司 [非常勤]
■田村 朋子 [非常勤]
■萩谷 英大 [非常勤]糖尿病外来
糖尿病は様々な合併症(脳梗塞・心筋梗塞・糖尿病網膜症・糖尿病性腎症など)をきたす病気です。早めに治療を開始することが大切です。
糖尿病は「自己管理病」です。糖尿病になっても悪化しないように 、合併症を起こさないように、また、健康な生活が送れるよう患者さんとともに取り組んでいます。
糖尿病療養指導士(看護師・管理栄養士・薬剤師)と連携をとり「食生活指導」「運動療法」「フットケア」「適切な薬のコントロール」などから患者さんのQOLの維持・向上を目指しています。表示を閉じる -
救急科


-
診療内容
地域における救急医療に貢献することをモットーとしております。
祥和会は、救急医療を担うことを条件に社会医療法人となっております。当院は二次救急病院としての使命を果たすため、当科と各科が協力し、バランスの良い救急医療に取り組む体制づくりに努めております。科目の特徴
近年では、当院が主な対象としている脳神経疾患以外の病気の搬送依頼も増加しており、高齢化が急速に進む今後、この傾向は強まるのではないかと考えております。患者さんの救命を最優先に、業務にあたっていきたいと思います。
医師

■救急外来医長 高畠 周
・日本循環器学会循環器専門医
・日本心血管インターベンション治療学会認定医
・日本内科学会総合内科専門医
■石根 周治 [非常勤]
救急受診のご案内
■当院は、入院を要する重症の患者さんに対し、24時間365日の医療を提供しております。
■万が一の際、直接ご来院になるときは、まず、電話でご相談ください。
084-931-8650 [病院代表]表示を閉じる -
リハビリテーション科


-
診療内容
脳卒中急性期治療において、早期からのリハビリ実施は予後を決めるうえで極めて重要です。当院では、入院当日、遅くとも翌日からリハビリを始めます。土日も休みなく365日リハビリを施行し、急性期に濃密な介入をすることで、患者さんの予後の改善に努めています。
科目の特徴
急性期早期から自宅退院、ないし回復期リハビリテーション病棟等への早期転院をめざしております。
また、リハビリ室には、多種類の装具を用意し、患者さんが実際に使用しながら、適切な選択ができるように助言しています。医師
■矢守 茂
・日本リハビリテーション医学会専門医
・日本リウマチ学会専門医
■松浦 大輔 [非常勤]
■永金 周臣 [非常勤]
当科の特徴
●ボトックス療法
脳卒中・脊髄損傷・脳性麻痺患者の痙縮に対するボトックス治療を行っております。痙縮軽減による機能改善に効果的とされています。表示を閉じる -
麻酔科


-
診療内容
●外科手術時の全身管理
●入院時の透析患者サポート
●人工呼吸中の患者サポート科目の特徴
麻酔科医の主な業務は「安全で快適に手術を受けていただくこと」です。
麻酔科医は手術中、患者さんの状態と手術の進行状況を見ながら、麻酔深度、呼吸の補助、血圧、脈拍の管理、輸液、血糖値、体温、疼痛の管理を行っています。
近年、手術中の管理だけでなく、術前術後管理が患者さんの予後に関係していると言われています。当院でも他科の医師、看護師、薬剤師などと協力して患者さんの周術期管理を行っています。
また、救急病棟における人工呼吸器補助の患者さんのサポート、入院前より維持透析を行っていた患者さんの入院中の透析管理なども行っています。医師
■田中 千春
・日本麻酔科学会麻酔科専門医
■渡邊 泰彦 [非常勤]
■吉田 翼 [非常勤]表示を閉じる -
整形外科


-
診療内容
四肢・関節などの運動器の外傷、加齢に伴う変性疾患、リウマチなどの炎症性疾患に対して確実な診断、適切な治療を行います。
科目の特徴
骨、関節、靱帯、腱、神経、筋肉など人が快適な生活を送るために必要な運動器を扱う分野です。外科的治療後のリハビリテーションも十分に行い、患者さんができるだけQOLの高い生活に戻れるように配慮しています。
医師
■整形外科部長 神原 淳
・日本整形外科学会 整形外科専門医
・日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
・日本骨粗鬆症学会認定医
・麻酔科標榜医
■丸山 正吾 [非常勤]
■島村 安則 [非常勤]
■古川 陽介 [非常勤]表示を閉じる -
形成外科


-
診療内容
外傷による変形・欠損、体表の形態異常、組織欠損などを可能な限り正常な状態に近づける治療を行っています。
また、入院患者さんの褥瘡治療とスタッフへのコンサルテーションを行っています。科目の特徴
頭の先からつま先まで、身体の広い範囲の再建・形成により、機能回復とQOLの向上を目的とする専門外科です。
医師
■井上 温子 [非常勤]
表示を閉じる -
小児神経科


-
診療内容
てんかんやけいれん性疾患を中心とする、小児神経疾患全般を専門的に治療します。先天異常・睡眠障害なども診療対象です。
科目の特徴
小児神経疾患を専門とする診療科はわが国ではまだきわめて少数です。てんかんを専門に診療する医師も少ない現状です。当専門外来ではすべて小児神経専門医、てんかん臨床専門医が診療にあたっています。
医師
■小林 勝弘 [非常勤]
・岡山大学 発達神経病態学 小児神経科 教授
■眞田 敏 [非常勤]
■柴田 敬 [非常勤]関係する症状
● けいれん、失神などの発作症状 ● 発達の遅れ、退行 ● 行動の異常 ● 麻痺などの運動障害 ● 自律神経不安定状態 ● 睡眠の障害、夜尿症 ● 意識障害その他小児の脳、神経系に関係する各種の症状
治療している主な病状
● てんかん ● 熱性けいれん ● 脳性小児まひ ● 発達の遅れ ● 頭部外傷 ● 筋肉の病気
表示を閉じる -
皮膚科


-
診療内容
日常的に発症する皮膚の疾患を中心に診療しています。
科目の特徴
皮膚に発症した不快な症状が悪化する前に、早めに受診されることをお勧めしています。
医師
■池田 美智子 [非常勤]
治療している主な病状
アトピー性皮膚炎、じんましん、しもやけ・ひび・あかぎれ、褥瘡(とこずれ)、あせも、日焼け、ヘルペス・帯状疱疹、水疱症、天疱瘡、掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)、乾癬、白癬(水虫・たむしなど)、イボ・ミズイボ、アザ・ホクロ、薬疹、膠原病、紫斑病、白斑、にきび、とびひ、虫さされ、疥癬(かいせん)、爪の病気、手足口病、脱毛症、性感染症
-
歯科(入院と紹介外来のみ)


-
診療内容
当院では、2015年6月から入院患者さんを対象に、歯科診療業務をスタートしました。診療室まで移動可能な患者さんに対しては、歯科診療室で診療を行いますが、移動困難な患者さんに対しては、病棟のベッドサイドで対応しています。
脳卒中患者の口腔内の特徴として、口腔の感覚障害や舌の運動障害といった口腔の障害、口腔内の清掃不良、口腔乾燥、義歯不適合などがあります。
特に、口腔の不潔な状態が続くと、口腔内で細菌が増殖し、歯周病の問題が生じるだけでなく、時には誤嚥性肺炎の原因になることがあります。
当科では、入院中の患者さんの口腔内の感染管理(口腔ケア・抜歯・虫歯治療)、栄養管理(義歯調整・嚥下訓練)、苦痛緩和(保湿・義歯調整)を行うことで、入院生活をサポートいたします。科目の特徴
●移動式の歯科ユニットや車椅子型チェアの導入によって、病棟のベッドサイドでも歯科治療を行います。
●退院後は患者さんのかかりつけ歯科診療所か、近隣の歯科診療所を紹介するなどして途切れることのない歯科診療を提供できるように努めています。
● 【歯科診療費】は、【医科入院費】とは別に請求いたします。院内で実施する治療は、原則として保険診療の範囲で行います。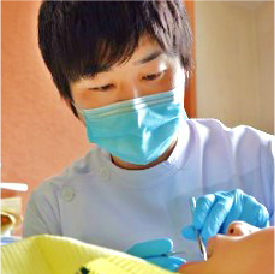
■歯科部長 松永 一幸
・日本歯周病学会 認定医
■坪井 綾香
■猪原 健 [非常勤]
■園井 教裕 [非常勤]表示を閉じる

-
診療科の詳細については、診療ガイド(電子ブック)をご覧ください。